
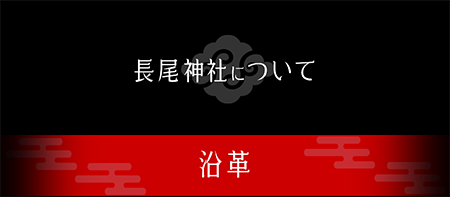
 長尾神社は、川崎市多摩区長尾(旧橘樹郡長尾村字西高根)の最高丘陵(海抜約82m)に鎮座します。
長尾神社は、川崎市多摩区長尾(旧橘樹郡長尾村字西高根)の最高丘陵(海抜約82m)に鎮座します。
当神社は江戸時代徳川幕府より、江戸近隣一帯の神主不在の神社を受け持つ白幡八幡大神(稲毛領稲毛総社総鎮守白幡八幡大神)のもと庇護されていました。
もとは、耕地長尾地域の鎮守で五所神社(五所権現)と称していました。
五所権現は、天文18年(1549年)に鎮座とも言われるが、武蔵野風土記稿に記されるよう明らかではありません。
明治時代となり神主も増え、白幡八幡大神は地元8つの神社を兼務する神社となりました。
明治42年(1909年)12月、長尾村字長峰宮谷
(現在の宮前区神木本町三丁目)にあった谷(神木)長尾地域の鎮守、赤城神社(赤城明神)と合併し、村社・長尾神社と改称され今日に至っています。
なお、この地方は、遠く戦国時代の戦火による災害を被ったためか、妙楽寺をはじめ多くの民家とともに文書その他の資料が消失してしまい、言い伝えによる他に由緒を知ることが
できません。
国常立命 ( くにのとこたちのみこと)
大己貴命 ( おおなむちのみこと )
大日霊貴命 ( おおひるめむちのみこと )
天忍穂耳命 ( あめのおしほみみのみこと )
富士浅間社 御嶽社 白山社 他に三基
 【石祠①】
【石祠①】
背面銘によると、「賽暦四甲戌歳(1754)5月吉日、江戸北八町堀石工和泉屋三良左衛門」、浅間神社と伝えられる。「富士浅間神社 村の東にあり、この辺の小名を富士谷と言えり」(武蔵野風土記稿)及び「無格社富士太神(東高根)を長尾神社に移転合併の聞届(明治44年7月)」の記録等はあるが、この祠そのものが富士太神浅間神社であるか定かではない。
【石祠②】
側面銘によると、「明治13年辰(1880年)9月」、御嶽神社と伝えられるが由来は不明である。
【石祠③】
側面銘によると、「明治22年辰(1889年)6月建造 氏子中」白山社と伝えられる。「白山社 山王社(妙楽寺の前にあり)の西に並べり」(武蔵野風土記稿) 及び「無格社日枝大神及び同稲荷明神(東高根) 石祠2基、無格社天照大神及び同白山神社(西高根)石祠1基、の4社を長尾神社地内に移転の願い聞届(明治41年1月)の記録等はあるが、事情は定かではない。
【石祠同型3基④】
台正面銘「氏子中」側面銘「明治22年6月建造」由来は不明である。上記移転4社の日枝大神(山王社)や稲荷明神が含まれるのかも知れない。


©️ nagaojinjya.com